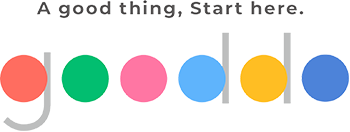1分でわかる!gooddo編集部まとめ
- タカラベルモント株式会社が、大阪・関西万博閉幕後のサステナビリティアクションプランを発表。
- 第一弾として、コシノジュンコ氏デザインの展示スタッフ用ユニフォームを教育機関へ寄贈。
- 寄贈先は全国の小・中・高校やデザイン・理美容分野の教育機関を対象に募集。
- 「未来のヘルスケア」をテーマにした万博展示のレガシーを次世代へ継承する取り組み。
未来をつなぐ「ユニフォーム寄贈プロジェクト」が始動
2025年の大阪・関西万博が閉幕した後、その熱気とともに残るのは、未来を見据えた数々の取り組みです。その中でも注目すべきは、タカラベルモント株式会社が発表したサステナビリティアクションプランの第一弾。デザイナー・コシノジュンコ氏が手掛けた展示スタッフ用ユニフォームを、全国の教育機関へ寄贈するというものです。
このユニフォームは、万博のテーマである「未来の光」をイメージしてデザインされ、未来への挑戦と可能性を象徴しています。寄贈先は、小・中・高校やデザイン・理美容分野の教育機関が対象。万博のレガシーを次世代へ継承し、未来を担う若者たちに「挑戦する心」を伝えることが目的です。

写真:タカラベルモント 万博展示スタッフユニフォーム
循環型社会への挑戦「THINK CIRCULAR for SPACE AGE」
「タカラベルモントは、万博展示で「未来のヘルスケア」をテーマに、2050年の宇宙時代における「真の美」を考える空間を提供しました。万博閉幕後も、地球環境の重要課題である資源循環に向き合い、「THINK CIRCULAR for SPACE AGE(宇宙時代の循環思考)」をアクションコンセプトに掲げています。
今回のユニフォーム寄贈もその一環。単なるリサイクルではなく、未来を創る教育の場に活用することで、循環型社会の実現を目指しています。これにより、万博の意義を単なる一過性のイベントに終わらせず、持続可能な社会への一歩として位置づけています。
寄贈先は全国の教育機関!未来を担う若者たちへ
寄贈先の募集は、万博閉幕後にタカラベルモントの公式サイトで詳細が公開される予定です。全国の教育機関が対象で、特にデザインや理美容分野の学校にとっては、世界的デザイナーが手掛けたユニフォームに触れる機会は貴重な学びとなるでしょう。
この取り組みは、単に物を寄贈するだけでなく、未来を担う若者たちに「挑戦する心」や「循環型社会の重要性」を伝える教育的な意義を持っています。ユニフォームをデザインしたコシノジュンコ氏が「未来を創るということは挑戦であり、実験そのもの。まずは『やってみる』ことが何より大切」と語るように、このユニフォームが次世代の創造力を刺激するきっかけとなることが期待されます。
寄贈先の募集詳細

コシノジュンコ氏デザインの展示スタッフ用ユニフォーム寄贈の応募方法など詳細については、万博閉幕後、順次当社コーポレートサイトにて公開されます。
未来を創る一歩に参加しよう
万博閉幕後も、企業としての使命を果たし続けるタカラベルモント。
教育機関の関係者の方々は、ぜひ公式サイトで寄贈先の募集情報をチェックし、応募してみてください。そして、私たち一人ひとりも、こうした取り組みに注目し、持続可能な未来を共に考えていきましょう!
関連画像・資料


問い合わせ先情報
【解説】万博のユニフォーム寄贈が意味するものとは?

万博で使われたユニフォームを寄贈するって、どういう意図があるんですか?

万博のユニフォームは、未来を象徴するデザインや理念が込められています。それを教育機関に寄贈することで、次世代の若者たちに「未来を創る挑戦心」や「循環型社会の大切さ」を伝えることができます。たとえば、学校でこのユニフォームを使ってデザインやサステナビリティについて学ぶ授業を行えば、未来を担う人材育成につながります。

「THINK CIRCULAR for SPACE AGE」って何ですか?

これは、タカラベルモントが掲げる循環型社会のコンセプトです。「宇宙時代」を見据えた持続可能な社会を目指し、資源を無駄にせず循環させる考え方を指します。たとえば、使い捨てではなく、再利用やリサイクルを重視する取り組みがこれに当たります。

こういう活動って、私たちにも関係あるんですか?

もちろんです!循環型社会を作るのは、企業だけでなく私たち一人ひとりの行動が大切です。たとえば、日常生活でリサイクルを意識したり、物を大切に使うことも循環型社会への一歩です。また、こうした取り組みに関心を持ち、周りに広めることも大きな貢献になります。

寄贈先の教育機関はどうやって選ばれるんですか?

寄贈先の募集は、万博閉幕後にタカラベルモントの公式サイトで詳細が発表されます。全国の小・中・高校やデザイン・理美容分野の教育機関が対象で、応募方法や選考基準については公式サイトで確認できます。

私たちができることは何ですか?

まずは、こうした取り組みに関心を持つことが大切です。そして、情報を広めたり、身近なところでサステナビリティを意識した行動を取ることができます。たとえば、学校や地域でリサイクル活動を提案するのも良いですね。