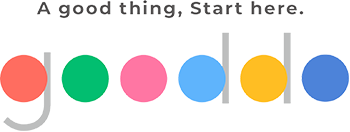1分でわかる!gooddo編集部まとめ
- ソニー損保が「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」により、「そらべあ発電所」を福島県の認定こども園子どもの森に寄贈。
- 本プログラムは、環境教育と再生可能エネルギーの普及を目的として、2009年に始動。太陽光発電を活用し、環境教育を推進する取り組み。
- 今回が39基目となり、2024年までに寄贈した37基でのCO2削減量は約427トンに到達。
- 寄贈記念式典では、子どもたちが紙芝居やクイズ、発電体験を通じて、地球温暖化やエネルギー問題について学んだ。
「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」とは?
地球温暖化やエネルギー問題が深刻化する中、再生可能エネルギーの普及は重要な課題となっています。そんな中、ソニー損保が展開する「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」は、環境保全と教育を組み合わせたユニークな取り組みとして注目されています。
このプログラムは、ソニー損保の自動車保険の年間走行距離を確認する仕組みを活用したもので、自動車保険契約者の実際の走行距離が契約時の予想より短かった場合、その分排ガス(CO2)排出量が減ることに着目し、その環境貢献をさらに広げる取り組みです。具体的には、予想より走らなかった距離の総計をもとに寄付額を算出し、NPO法人そらべあ基金を通じて太陽光発電設備「そらべあ発電所」を全国の幼稚園・保育園・こども園に寄贈しています。
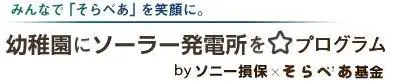

イメージ画像:寄贈された太陽光パネル
福島県での寄贈と環境教育の広がり
2025年8月、このプログラムによる39基目の「そらべあ発電所」が福島県会津若松市の認定こども園子どもの森に寄贈されました。同園は自然豊かな環境を活かし、「みつけたね、じぶんのいろ」という理念のもと、子どもたちの個性を尊重した保育を行っています。
寄贈記念式典では、子どもたちが「そら」と「べあ」の紙芝居やクイズ、発電実験を通じて地球温暖化や環境を守るための取組みや再生可能エネルギーの仕組みを学びました。園長先生は「太陽光発電という具体的な形で環境への取り組みを子どもたちと共有できることは非常に貴重」と語り、子どもたちが「おひさまの力で電気がつくんだ!」と驚きと理解を示した様子を紹介しています。
このような環境教育は、子どもたちにとって地球温暖化やエネルギー問題を「遠い世界の話」ではなく、「自分たちの生活とつながること」として捉えるきっかけになります。


CO2削減の実績と未来への期待
「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」による寄贈はこれまでに全国で39基となり、2024年までに寄贈した37基によるCO2削減量は約427.83トンに達しています。未来を担う子どもたちに対する環境教育に加え、再生可能エネルギー普及活動の継続的なサポートにより、環境保全に貢献していると言えます。
さらに、こうした取り組みは、子どもたちだけでなく地域全体に環境意識を広げる効果も期待されています。認定こども園子どもの森では、保護者や地域と連携しながら、環境教育を通じて持続可能な社会づくりに貢献していく構想が進められています。
私たちも、こうした取り組みに注目し、日常生活の中で環境への配慮を意識することが大切です。ぜひ、再生可能エネルギーや環境教育について考え、行動を起こしてみませんか?
関連画像・資料



問い合わせ先情報
【解説】子どもたちが学ぶ機会を提供する「そらべあ発電所」とは?

「そらべあ発電所」って何ですか?

「そらべあ発電所」は、太陽光発電を活用した設備で、幼稚園・保育園・こども園に寄贈されるものです。子どもたちが再生可能エネルギーについて学び、地球温暖化や環境問題を考えるきっかけを作るために設置されています。
ソニー損保の「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」によって寄付された資金を活用して、NPO法人そらべあ基金を通じて寄贈されています。

「幼稚園にソーラー発電所を☆プログラム」ってどんな仕組みですか?

ソニー損保の自動車保険のご契約いただく時に年間走行距離を確認する仕組みを活用したプログラムで、自動車保険契約者の実際の走行距離が契約時の予想より短かった場合、その分排ガス(CO2)排出量が減ることに着目した仕組みです。その環境貢献をさらに広げるため、走らなかった距離をもとに寄付額を算出し、NPO法人そらべあ基金を通じて太陽光発電設備を幼稚園・保育園・こども園に寄贈しています。
たとえば、あなたの車で走る距離が予定より少なかったら、その分地球に優しい行動をしたことになります。その「優しさ」を形にして、未来の子どもたちに役立てる取り組みなんです。

寄贈された園ではどんなことが行われるんですか?

寄贈された園では、環境学習や発電体験が行われます。たとえば、手回し発電機を使って電気を作る実験をしたり、地球温暖化についての紙芝居を見たり絵本を読んだり、環境について学んだりします。
こうした体験を通じて、子どもたちは「電気ってどうやって作られるの?」という疑問を持ち、自然の恵みを活用する大切さを学びます。

子どもたちが環境問題を学ぶことって、どんな意味があるんですか?

子どもたちが環境問題を学ぶことは、未来の社会をより良くするための第一歩です。たとえば、電気を無駄にしないようにしたり、自然を大切にする行動を取ることで、地球を守る力になります。
環境問題は難しい話に思えるかもしれませんが、子どもたちが「自分にできること」を考えるきっかけを持つことが大切なんです。

私たちも何かできることはありますか?

もちろんあります!たとえば、家で電気をこまめに消したり、リサイクルを心がけたりすることが、環境を守る行動につながります。また、地域の環境教育イベントに参加してみるのも良いですね。
小さな行動でも、みんなが協力すれば大きな変化を生むことができます。まずは、身近なところから始めてみましょう!