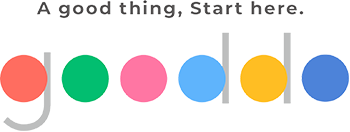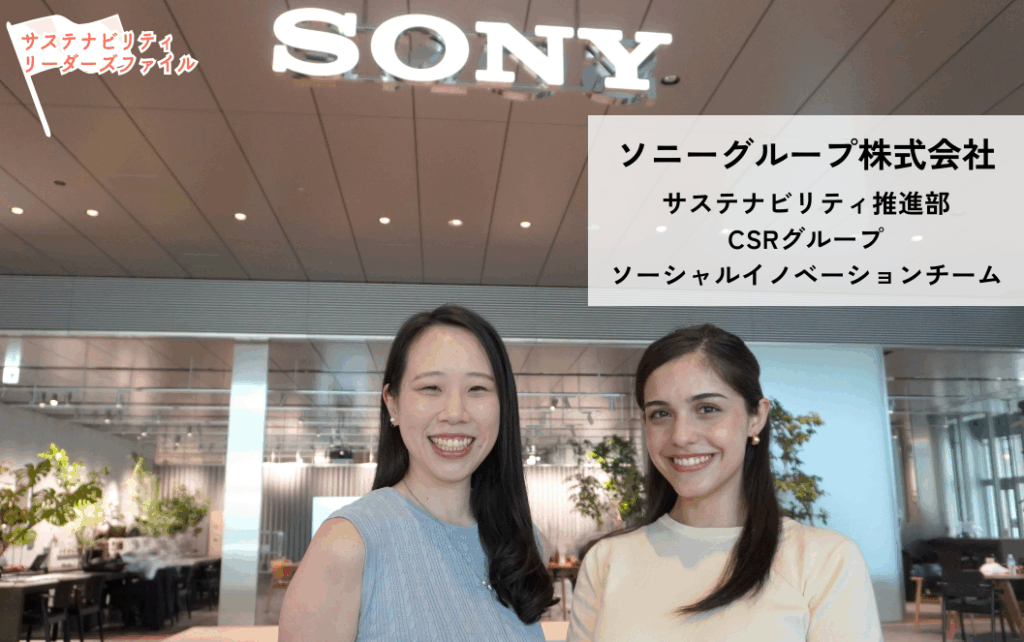
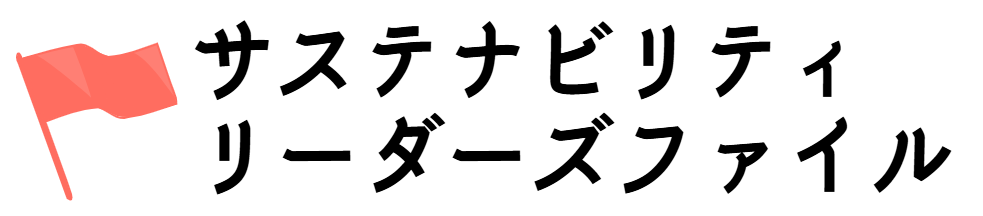
サステナビリティのリーダーに密着!
ビジネスと社会貢献を両立する人と企業の深掘りシリーズ
子どもたちの“好奇心”を育てる──。 ソニーが展開する次世代教育プログラム「CurioStep(キュリオステップ)」は、STEAM分野を横断する多彩な学びを、夏休みを中心に全国の子どもたちに届けています。
参加希望の子どもは年々増加し、社員ボランティアの枠も応募多数で“お断り”が出るほどの人気ぶり。 なぜ今、ソニーが教育支援に力を入れるのか? そして、なぜこれほどまでに社員の心を動かすのか──。 運営を担うソニーグループ株式会社 サステナビリティ推進部 CSRグループ ソーシャルイノベーションチームの皆様にお話を伺いました。
取材・編集:gooddo編集部

好奇心を育むSTEAM教育を──CurioStepが生まれた理由
まずはCurioStepという取り組みについて、概要を教えてください。
はい、CurioStep(キュリオステップ)は、小学生を中心とした子どもたちを対象に、ソニーが行っている教育支援プログラムです。ワークショップは毎年ソニーの拠点がある地域で開催していて、特に夏の企画である「サマーチャレンジ」では、ワークショップを一斉に開催しており、全国の子どもたちに参加してもらっています。
プログラミングやアート、音楽、ものづくりなど、STEAM領域※と呼ばれる幅広いジャンルを扱っているのが特徴です。
たとえば、紙コップを使ってスピーカーを作るワークショップや、ソニー製品を実際に分解して仕組みを学ぶ体験、ドライフラワーを使ったアート作品づくりなど、学校ではなかなか体験できないような本格的な内容を、遊びの延長のような感覚で楽しめるように設計しています。
これは、「社会の大きな変化に対応するには、創造性や問題解決力が求められる」という私たちの強い想いからできたプログラムなんです。子どもたちが“知らないことを知る楽しさ”“好きなことに出会う喜び”を実感できるように、ソニーならではのテクノロジーとクリエイティビティを生かした学びの機会を提供しています。
※Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術・リベラルアーツ)、Mathematics(数学)の略

もともと教育支援はソニーのカルチャーとしてあったのでしょうか?
実は、ソニーが教育支援に取り組むようになったのは、創業期にまでさかのぼることになります。1946年、ソニーの創業者のひとりである井深大が、設立趣意書の中で「国民科学知識の実際的啓蒙活動」をソニーの創設目的の一つとして掲げていました。つまり、技術の力をビジネスに生かすだけでなく、社会の再建や文化の発展に貢献することが、ソニーの根幹にある考え方だったんです。
この理念が、現在の教育支援活動にも受け継がれていて、ソニーの製品・コンテンツ・技術・人材といった資源を生かして、未来を担う子どもたちへの支援を行うという形に繋がっています。
つまり教育支援は「戦後復興のために科学技術を広める」という想いから始まった、ソニーの創業理念の延長線上にある活動なんです。時代の変化にあわせて形は変えていますが、根っこの部分は創業当初からずっと大切にされてきたものだと感じています。

CurioStepサマーチャレンジが子どもに届ける「成功体験」
2020年の開始以来、プログラムはどのように進化してきましたか?
もともとは科学教育を中心にしたプログラムでしたが、現在ではSTEAM領域に関わるさまざまな体験を提供するようになっています。
例えば、ワークショップの数も増えていて、今年実施した「CurioStep サマーチャレンジ2025」では、ライフプランニング体験や、「ドライフラワーを使ったアート作品づくり」など、新たなテーマに挑戦しました。社員が講師として参加し、実際の製品を分解するワークショップや、ソニーのテクノロジーを生かした音楽・ゲーム関連のプログラムもあります。
また、これまでオンラインとリアルの両方で参加できる機会を用意するなど、参加のハードルを下げる工夫もしてきました。「おうちdeチャレンジ」といった自宅学習向けのコンテンツも好評で、科学工作のレシピなど、自由にアクセスできる教材を充実させています。 その結果、嬉しいことに参加希望者も年々増え、今年は過去最多の応募数を記録しました。プログラムの内容も、運営体制も、少しずつですが確実に進化していると感じています。
子どもたちには、どんなことを持ち帰ってほしいですか?
大きく分けて、2つのことを持ち帰ってほしいと考えています。
まず1つ目は「学びの本質的な理解」です。ワークショップごとに伝えたい学びのテーマがあり、たとえば「紙コップスピーカー」のワークショップでは、音が聞こえる仕組みや、コイルと電気による磁力発生の原理などを体験しながら学べるようになっています。ただ楽しいだけでなく、きちんと理科的な知識を“自分の手で作りながら”理解してもらえるように設計しています。
そして2つ目は「達成感や成功体験」です。自分で作ったものがちゃんと動いたときの「できた!」という実感、それを誰かに見せたり話したりする喜びは、自己肯定感や次のチャレンジへの原動力につながります。
この2つ──知的な学びとポジティブな感情の両方を得て、「またやってみたい」「次はこんなことをしてみたい」と思ってもらえたら嬉しいですね!好奇心を育むきっかけになることが、私たちが一番大切にしていることなんです。
実際に、参加したお子さんや保護者の声で印象的だったものはありますか?

はい、毎回たくさんの感想をいただいていて、私たちにとってもとても励みになっています。
例えば、先ほどお伝えしたソニー製品を社員の立ち会いのもと安全に分解するワークショップでは、「分解して、外からでは見えない部分が見られて楽しかった」「家ではできないことができて面白かった」といった声もありました。
家庭ではできない“特別な学び”が、子どもたちの好奇心を刺激する機会になればと思っています。
また、ご参加していただいた保護者の方からは「子どもが以前よりも自分でできることが増えたと気づきました」「私は教えてあげられないけれど、こういう機会をつくっていただけて本当にありがたかった」といった声がありました。
子どもたちの成長を身近に感じてもらえる体験として、保護者の皆さんにとっても大切な時間になっていることが嬉しいですね。

創業理念 × 現場の創意工夫で、未来を切り拓く
インクルージョンに配慮したワークショップもあると伺いました。
はい、私たちは「インクルージョン・ワークショップ」という、障がいの有無にかかわらず誰もが参加できるワークショップも実施しています。運営を担っているのは、ソニーの特例子会社である「ソニー・太陽株式会社」の社員たちで、この会社では障がいのある社員が全体の約6割を占めています。
このワークショップでは、ものづくりの楽しさを共有しながら、ダイバーシティやインクルージョンの概念を“体験として”伝えることを目的としています。
もちろん、どのワークショップにも障がいの有無にかかわらずご参加いただけるのですが、実際には「他のワークショップには少し参加しづらいかも…」と感じてしまうご家庭もいらっしゃいます。
そんな中で、スタッフ側に障がいのある社員がいるということが、「ここなら行ってみようかな」と安心してもらえるきっかけになっていることも多いです。
障がいのある・なしに関係なく、お互いを自然に理解し合えるきっかけになるような場を目指しています。これはソニーの教育支援だからこそ実現できる、もう一つの大切な側面だと思っています。
CurioStepでは、現場の社員の方々も多く関わっているそうですね。
そうなんです。CurioStepのプログラムには、ソニーグループ各社の社員が多く関わってくれています。私たち本社側のチームは少人数ですが、実際のワークショップやプログラム運営には、現場のエンジニアやクリエイターなど、各事業部の社員たちが自ら手を挙げて参加してくれています。
こちらからお願いする前に、「やってみたい」と手を挙げてくれる社員が多く、参加希望者が多すぎてお断りするケースもあるほどです。
普段の業務では、製品の“ユーザー”と直接関わる機会がない社員も多いです。でも、このプログラムを通して、目の前で子どもたちの喜ぶ姿や反応を見ることができる。自分の仕事の意味を実感できる場でもあるのだと思います。
業務外でも「子どもたちに伝えたい」という気持ちで参加してくれる社員が多く、それもソニーらしさの1つだと思います。

今後、CurioStepやサマーチャレンジをどう展開していきたいですか?
今後も変わらず大切にしていきたいのは、「子どもたち一人ひとりの好奇心を育むこと」です。
社会がますます複雑で予測困難になる中で、これからの子どもたちには、創造性や問題解決力が一層求められるようになると思っています。だからこそ、ソニーの強みであるクリエイティビティとテクノロジーを生かして、子どもたちがワクワクしながら学べる体験を届けていきたいと考えています。
ワークショップやプログラムの内容も、時代や子どもたちの関心に合わせてアップデートし続けていく予定です。「知らなかった世界に触れる」「好きなことを見つける」そんなきっかけを提供し、未来を動かす“夢と力”につながるような学びの場をこれからも育てていきたいです。
関連画像・資料