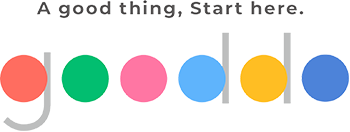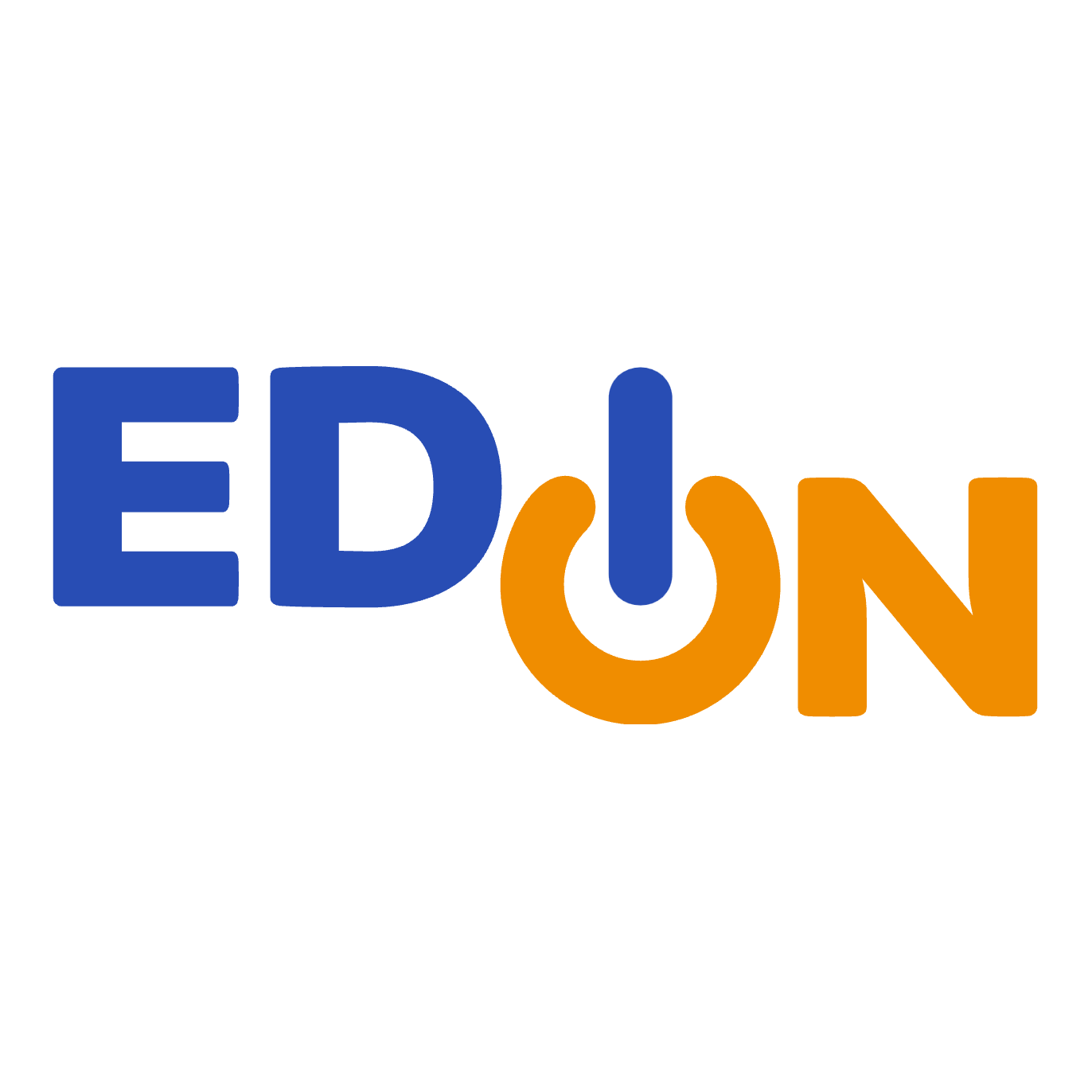仕事帰りのスーパーで、賞味期限が近い食品を目にして「まだ食べられるのに…」と思ったことはありませんか?
実は、私たちの暮らしの身近な場所で起きている「フードロス」は、世界規模の社会課題として注目されています。
食べられるのに捨てられる食品は、家庭だけでなく企業や生産者側など色々な場面で発生しており、資源や労力の無駄遣いに加え、環境負荷や経済的損失、さらには飢餓問題にも関わる深刻な問題です。
「食べきる・分け合う・活かす」――私たち一人ひとりの工夫や、企業、地域での取り組みが広がることで、資源や環境を守り、未来の食卓を豊かにする一歩となります。
EXPLANATION
フードロス問題とは?
フードロスとは、「本来なら食べられる食品」が様々な理由で捨てられてしまうこと。
廃棄には家庭から出るロス(家庭系)と、企業・販売・飲食などで出るロス(事業系)の2種類があり、売れ残り/賞味期限切れ/食べ残し/規格外など、消費者だけでなく小売・生産者などサプライチェーン全体で発生しています。
・事業系食品ロス:スーパーや飲食店、工場などで発生するもの
・家庭系食品ロス:家庭で食べきれずに捨ててしまうもの
日本では年間約523万トンもの食品が廃棄されており、その量は東京ドーム約5個分、国民一人あたりだと毎日おにぎり1個分(約114g)の食品を捨てている計算に相当すると言われています。
フードロスってなにが問題?
フードロスが問題である理由は、大きく3つあります。
- 資源の無駄遣い
- 食品を作るには水・肥料・燃料など多くの資源が必要です。それが丸ごと捨てられることは、資源もお金も労力も同時に捨てていることになります。
- 環境への負担
- 廃棄された食品を焼却や埋め立てすると、温室効果ガスが発生し、地球温暖化の原因になります。
- 特に水分を多く含む食品の焼却には多くのエネルギーが必要で、処理費用もかかります。焼却時にはCO₂が排出され、焼却後の灰を埋め立てる土地も必要です。例えば、フードロス100トンを削減できれば、46トンのCO₂削減に相当します。
- 社会的損失
- 食べ物が足りない人や地域がある一方で廃棄されている食品があることは、食の公平性や経済の効率性の観点からも問題です。
私たちにできること
まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を、「活かす」ことがフードロス削減の第一歩です。日常のちょっとした工夫や選択で、楽しみながら地球にも優しい行動ができます。
- フードロス削減商品を「選ぶ」
- 規格外野菜や余剰食品を使った加工品、企業が取り組むフードロス削減商品を選ぶことで、企業活動を応援し、社会全体での食品ロス削減に参加できます。
- 食べきれる量を「買う・作る」
- スーパーで買うときや家庭で調理するとき、食べきれる量を意識することで、無駄を減らすことができます。
- 保存やリメイクで「活かす」
- 余った食材は冷凍保存やアレンジ料理に活用。少しの工夫で最後まで美味しく食べられます。
- 身近な人に「お裾分けする」
- 食べきれない食材や料理は、家族や友人、近所の人に分けることで無駄を減らせます。さらに、食べ物を通じて人とのつながりも生まれる、気軽で楽しい方法です。
- 意識を広める・参加する
- 地域の食品ロス削減イベントや啓発キャンペーンに参加することで、楽しみながら学び、周りの人にも行動を広げられます。
よくある質問

フードロスって何ですか?

本来食べられる食品が、家庭やスーパー、飲食店などで捨てられてしまうことを指します。賞味期限切れや売れ残り、食べ残し、規格外品など、さまざまな理由で発生します。

どれくらい深刻な問題ですか?

日本では年間約523万トンの食品が廃棄されており、国民一人あたり毎日おにぎり1個分(約114g)の食品を捨てている計算です。資源の無駄遣いや環境負荷、社会的損失につながる深刻な課題です。

家庭でできるフードロス対策はありますか?

買う・作る量を調整する、食材を冷凍保存やアレンジ料理で活かす、余った食材を家族や友人に分けるなどの工夫ができます。日常のちょっとした行動で大きな効果が期待できます。

企業や地域の取り組みにはどんなものがありますか?

規格外野菜や余剰食品を使った商品開発、飲食店の持ち帰りサービス、地域での食品ロス削減イベントなどがあります。私たちが参加することで、活動を応援することも可能です。

フードロス削減商品って安全ですか?

格外野菜や余剰食品を使った商品は、食品衛生の基準を満たしているので安心です。スーパーや専門メーカーが作っているものが多く、味や品質も通常商品と変わりません。

子どもや家族も参加できますか?

はい。食べきれる量を意識した調理や余った食材の活用、地域イベントへの参加などを通じて、楽しみながら学べます。食育としても最適で、家庭での習慣づくりにもつながります。