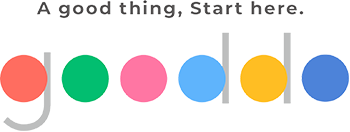1分でわかる!gooddo編集部まとめ
- アストラゼネカとみどりのドクターズが高校生向け探究型授業「未来探究」を実施。
- 気候変動が健康に与える影響を学び、解決策を考える4カ月間のプログラム。
- 成果は2025年の大阪・関西万博英国パビリオンで発表予定。
- 気候変動による健康リスクは深刻で、2050年までに1,450万人が亡くなる可能性も。
- 気候変動を「21世紀最大級の公衆衛生の危機」と捉え、次世代の行動を促進。
気候変動と健康の関係を高校生が探究する新プログラム
気候変動が私たちの健康にどのような影響を与えるか、考えたことはありますか?熱中症や感染症の増加、大気汚染による呼吸器疾患など、気候変動は私たちの命に直結する問題であり、「21世紀最大級の公衆衛生の危機」とも言われています。
そんな中、アストラゼネカとみどりのドクターズが高校生を対象にした探究型授業「未来探究」を開始しました。このプログラムでは、気候変動が健康に与える影響を学び、未来の地球と人々の健康を守るためにどのような行動ができるかを考えます。
参加するのは、探究型授業に積極的に取り組む雲雀丘学園高と灘高の生徒たち。約4カ月間にわたり、専門家のレクチャーを受けながら課題を設定し、情報収集や議論を重ねることで、未来を守るための行動を模索します。そしてその成果を、2025年の大阪・関西万博英国パビリオンで発表する予定です。
気候変動を「自分事」として捉える教育の重要性
世界経済フォーラムの報告によると、2050年までに気候変動の影響でさらに1,450万人が命を落とす可能性があるとされています。一方で、日本の若者の気候変動に対する危機感は諸外国と比べて低いという調査結果もあります。このギャップを埋めるためには、気候変動を「自分事」として捉える教育が必要です。
今回のプログラムでは、医師や気象予報士などの専門家が生徒たちをサポート。気候変動がもたらす健康被害を具体的に学ぶことで、問題の深刻さを実感し、行動につなげる力を育みます。例えば、熱中症対策の啓発活動や、地域での環境保護活動の提案など、具体的な行動を通じて社会に影響を与えることが期待されています。
大阪・関西万博で世界に発信する高校生の声と、私たちにできること
プログラムの成果は、2025年9月16日に大阪・関西万博の英国パビリオンで発表されます。生徒たちは「自分たちと地球の健康を守るためにできること」を世界に向けて提案します。この発表が、気候変動への理解や行動の輪を広げるきっかけとなることが期待されています。
アストラゼネカの堀井貴史社長は、「気候変動と健康の問題に取り組むことは、子どもたちの未来の健康を守ること」と述べています。また、みどりのドクターズの佐々木隆史代表理事は、「いのちを守るために何ができるか、一緒に考えていきましょう」と呼びかけています。
気候変動は、未来の世代だけでなく、今を生きる私たちにも影響を及ぼします。このプログラムを通じて生徒たちが示す行動は、私たち一人ひとりが考えるべき課題でもあります。まずは、気候変動と健康の関係について知り、日常生活の中でできることから始めてみませんか?
関連画像・資料


問い合わせ先情報
【解説】気候変動と健康の関係って何?

気候変動が健康に影響を与えるって聞いたんですけど、具体的にはどんな影響があるんですか?

気候変動は、熱中症や感染症の増加、大気汚染による呼吸器疾患など、私たちの健康に直接的な影響を与えます。例えば、気温が上昇すると蚊が繁殖しやすくなり、デング熱やマラリアのような感染症が広がりやすくなります。また、異常気象による災害が増えることで、けがやストレスも増加します。

どうして日本の若い世代は気候変動に対して楽観的なんでしょうか?

日本では、気候変動の影響がまだ身近に感じられないことが理由の一つかもしれません。例えば、海外では洪水や干ばつが頻発している地域もありますが、日本では比較的災害対策が進んでいるため、危機感が薄いのかもしれません。ただし、気候変動の影響は確実に広がっているので、楽観視せずに行動することが大切です。

高校生が気候変動に取り組む意義って何ですか?

高校生は未来を担う世代です。彼らが気候変動について学び、行動を起こすことで、社会全体の意識を変えるきっかけになります。例えば、学校での環境保護活動やSNSでの情報発信など、若い世代の行動は周囲に大きな影響を与える力があります。

気候変動に対して、私たちができることって何ですか?

日常生活でできることはたくさんあります。たとえば、電気を節約する、ゴミを減らす、地元の環境活動に参加するなどです。気候変動は大きな問題ですが、一人ひとりの行動が集まれば、社会全体を変える力になります。気候変動について知識を深め、周囲に伝えることも重要です。まずは、自分ができることから始めてみましょう!